金利を制する者が資産形成を制す。今日から始める、お金がお金を生む仕組みの作り方
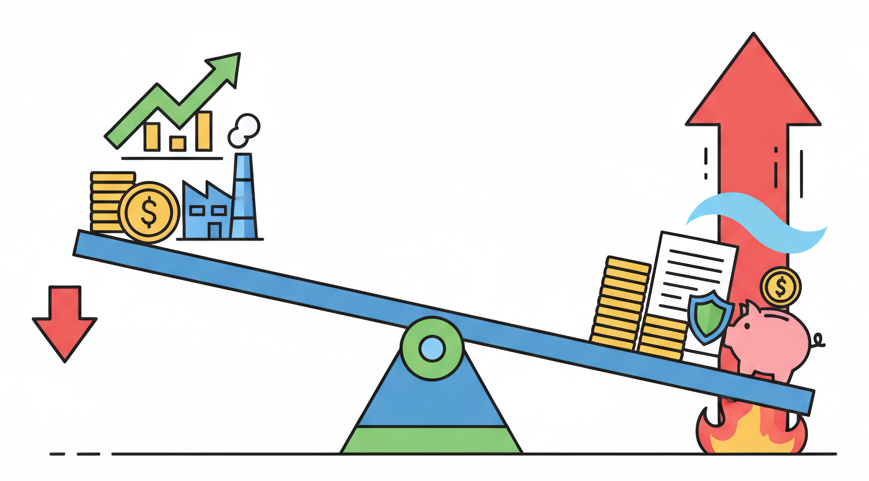
【冒頭まとめ】この記事を読めば、金利が「わからない恐怖」から「頼れる味方」に変わります
「日銀が金利の引き上げを検討」「アメリカの金利上昇で株価が下落」…こんなニュースを見て、「よくわからないけど、なんだか怖いな」と感じていませんか?
しかし、金利の正体は、経済の体温計のようなもの。仕組みさえわかれば、私たちの資産を守り、さらには賢く増やすための最強の武器になります。この記事では、金利の基本から、ニュースの裏側、そして金利の変動をチャンスに変える具体的な方法まで、投資仲間として同じ目線で、どこよりも分かりやすく解説します。読み終わる頃には、漠然とした不安が「なるほど、そういうことか!」という自信に変わっているはずです。
ニュースの主役「政策金利」の正体は、経済の”司令塔”だった
テレビやネットで毎日のように聞く「金利」のニュース。その中心にいるのが、「政策金利(せいさくきんり)」という言葉です。なんだか難しそうですが、要は経済全体の”司令塔”のようなものだと考えてください。
誰が、何のために決めているの?
この司令塔の役割を担っているのが、日本銀行(日銀)です。日銀は、日本で唯一お札を発行できる、銀行のなかの銀行、いわば「親玉」です。
日銀は年に8回、「金融政策決定会合」という会議を開き、経済の専門家たちが集まって、今の日本の景気は「熱すぎるのか」「冷えすぎているのか」を判断します。
- 景気が悪い(デフレ)時:世の中にお金が出回らず、モノが売れない状態。日銀は経済を元気にするため、「金利を下げる」という栄養ドリンクを注入します。
- 景気が良い(インフレ)時:世の中にお金が出回りすぎて、モノの値段が上がりすぎている状態。日銀は経済を少し落ち着かせるため、「金利を上げる」という冷却シートを貼ります。
このように、政策金利は、物価の安定と経済の健全な発展という、壮大な目標のための「調整つまみ」なのです。
日銀が動くと、なぜ私たちの生活に影響が?
では、日銀が「調整つまみ」を回すと、なぜ私たちの生活にまで影響が及ぶのでしょうか。
それは、私たちが普段利用している銀行(三菱UFJ、三井住友など)が、日銀の決定に直接影響を受けるからです。
- 日銀が金利を下げる
- 銀行は、日銀からより低い金利でお金を借りられるようになります。
- その結果、銀行は企業や私たち個人にも、低い金利でお金を貸し出せるようになります。
- → 住宅ローンや自動車ローンの金利が下がり、お金を借りやすくなります。企業の設備投資も活発になり、景気が上向くことが期待されます。
- (反面、預金金利はほぼゼロになり、銀行にお金を預けても増えない時代になります)
- 日銀が金利を上げる
- 銀行は、日銀からお金を借りる際の金利が高くなります。
- その結果、銀行は私たちにも高い金利でお金を貸さざるを得なくなります。
- → 住宅ローンの金利が上がり、お金を借りにくくなります。企業の活動も少し鈍くなり、過熱した景気が落ち着く方向に向かいます。
- (一方で、預金金利が上昇し、銀行にお金を預けるメリットが少しずつ出てきます)
ニュースで「日銀が…」と大騒ぎになるのは、この決定が、私たちの預金やローン、ひいては社会全体の景気にまで影響を与える、超重要な発表だからなのです。
「金利が上がると、なぜ株価は下がるの?」投資家が恐れる本当の理由
投資を始めると必ず耳にする格言、「金利は株価の敵」。これはどういった意味なのでしょうか?
1:企業の利益が減ってしまうから
多くの会社は、銀行からお金を借りて設備投資をしたり、新しい事業を始めたりしています。金利が上がると、この借金の返済額(利息)が増えてしまいます。

例えば、100億円を借りている会社の金利が1%上がると、単純計算で年間の利息負担が1億円も増えることになります。これは会社の利益を直接圧迫しますよね。利益が減れば、その会社の株価が下がるのは自然な流れです。特に、多額の借金をして急成長を目指すIT企業などは、金利上昇の影響を大きく受けやすいと言われています。
2:株より「安全な選択肢」の魅力が増すから
もう一つの理由は、投資家のお金の流れが変わるからです。
想像してみてください。今、あなたの手元に100万円あるとします。
- 金利がほぼ0%の世界:銀行に預けてもお金は増えません。少しリスクをとってでも、株式投資で5%のリターンを狙いに行った方が魅力的ですよね。お金は株式市場に集まります。
- 金利が3%の世界:銀行に預けるだけで、何もしなくても(ノーリスクで)年間3万円が増えることになります。一方、株式投資は値下がりのリスクがあります。「リスクを冒して5%を狙うより、安全な預金で3%もらえるなら、そっちでいいや」と考える人が増えてきます。
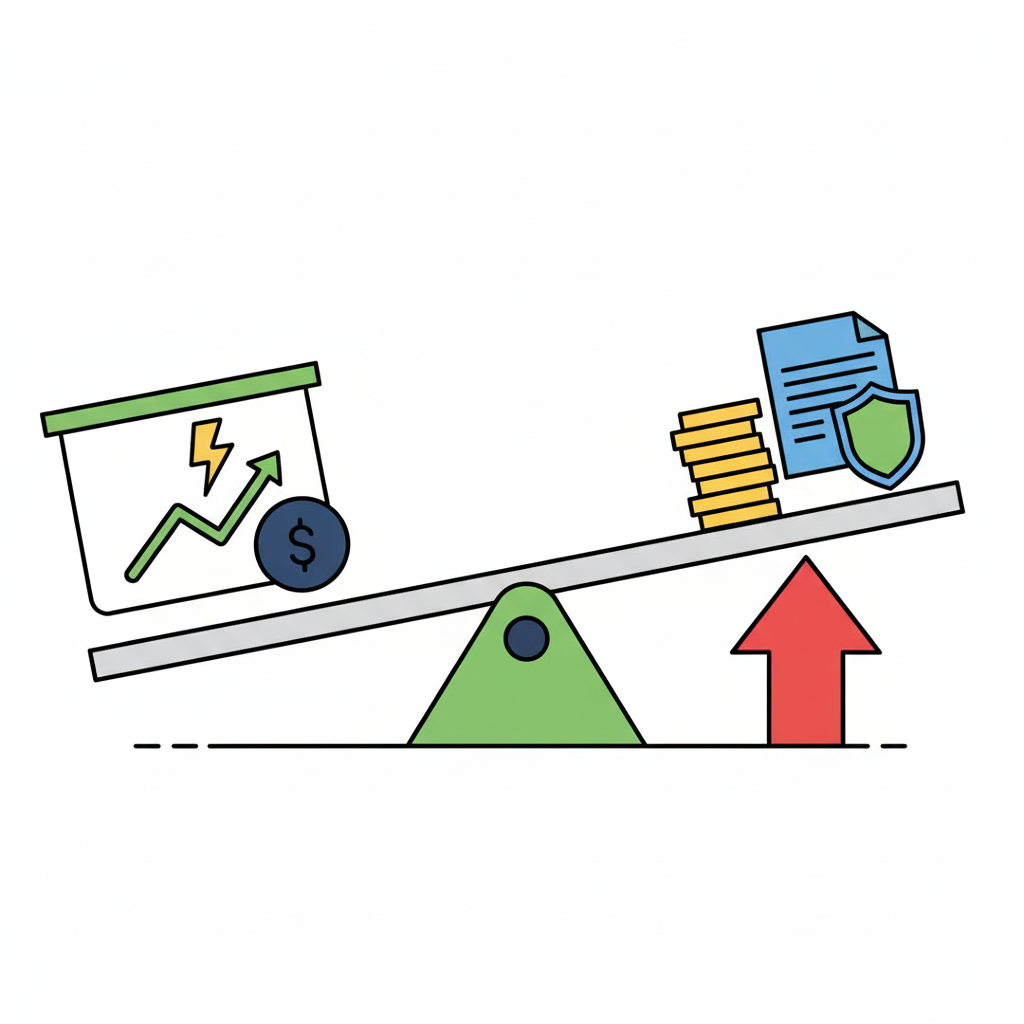
このように、金利が上がると、リスクのある株式から、安全な預金や国債(国が発行する債券)へとお金の大移動が起こります。株を買う人が減り、売る人が増えるため、株価は全体的に下がりやすくなるのです。これが、投資家が金利上昇を警戒する大きな理由です。
金利上昇はピンチ?いや、”お宝”を探すチャンスです!
ここまで聞くと、「やっぱり金利上昇は怖いことばかりだ…」と感じるかもしれません。でも、視点を変えれば、これは新たなチャンスの始まりでもあります。どんな状況でも、輝きを増す「お宝」のような投資先は存在するのです。
1. 銀行株
金利上昇で真っ先に恩恵を受けるセクターの一つが銀行です。銀行の主なビジネスは、預金者から低い金利でお金を集め、企業や個人に高い金利で貸し出すこと。その金利差(利ざや)が銀行の儲けになります。
金利が上昇する局面では、この利ざやが拡大しやすくなるため、銀行の収益が改善するとの期待から株価が上がりやすくなります。実際に、日銀がマイナス金利解除を決定した際、メガバンクの株価が大きく上昇したのが記憶に新しいところです。
2. 債券(新規投資)
金利と債券価格の関係はシーソーのようで、金利が上がると債券の価格は下がります。このため、すでに債券を持っている人にとってはマイナスに働くことがあります。
しかし、これから債券に投資する人にとっては、絶好のチャンスになります。 なぜなら、新しく発行される債券の利率(クーポン)が高くなるからです。以前は年0.5%の利息しかつかなかった国債が、年1.5%で買えるようになるイメージです。株のように大きな値上がりは期待できませんが、国が発行する安全な債券で、決まった利息をコツコツ受け取れるのは、守りの資産運用を考える上で非常に魅力的です。
3. 高金利通貨
これは少し中級者向けですが、金利は国ごとに異なります。例えば、日本が低金利でも、アメリカが高金利という状況は頻繁に起こります。そうした場合、円をドルに換えてドルで預金するだけで、日本の銀行預金とは比べ物にならない高い金利を受け取ることができます。
もちろん為替変動のリスクはありますが、金利差を狙った投資は、金利上昇局面で有効な選択肢の一つとなります。
金利上昇局面は、すべての株が下がるわけではありません。むしろ、経済が正常化していく証と捉え、お金の流れの変化を読んで投資先を選ぶ、エキサイティングな時期とも言えるのです。
結論!金利を味方につけて「ほったらかし」でお金を増やす仕組み
さて、ここまで金利の仕組みや影響について見てきました。では、この知識を、私たちのような普通の会社員や主婦が、どうやって日々の資産形成に活かせばいいのでしょうか。 複雑な金融商品の売買をする必要はありません。金利の動きに一喜一憂しない、「ほったらかし」の仕組みを作ることです。
基本戦略は「ドルコスト平均法」でのインデックス投資
結論から言うと、基本戦略はこれまで通り「全世界株式(オルカン)」や「S&P500」といったインデックスファンドを、毎月決まった額、淡々と積み立て続けることです。これが最強の土台になります。
- 金利が上がって株価が下がった時:これは「バーゲンセール」の合図です。「わ、下がって怖い」ではなく、「いつもより安くたくさん買える、ラッキー!」と考えましょう。同じ積立額でも、より多くの口数を買うことができます。
- 金利が下がって株価が上がった時:もちろん嬉しいですよね。資産が増えていくのを楽しみましょう。
このように、ドルコスト平均法は、金利の変動による株価の上下動すらも、長期的に見ればすべて自分のプラスに変えてくれる魔法のような手法なのです。ウォーレン・バフェットのような投資の神様でさえ、市場のタイミングを完璧に読むことはできないと言います。だからこそ、私たちは感情を排して、ルール通りに積み立てを続けることが何より大切なのです。
金利変動への”備え”としてのポートフォリオ
基本はインデックス投資で全く問題ありません。ただ、もしもう少し金利の変動リスクに備えたい、守りの意識を強くしたいと考えるなら、「債券」を少しだけ資産に加えることを検討してみましょう。
一般的に、株と債券は異なる値動きをする傾向があります。株価が下がる局面で、債券価格は安定、もしくは上昇することがあります。そのため、資産全体に占める株式の割合を少し減らし、その分を債券ファンドや債券ETFに振り分けることで、資産全体の価格変動をマイルドにする効果(クッション効果)が期待できます。
具体的なアクションプラン
- まずは新NISA口座を開設する:まだの人は、これが全ての始まりです。ネット証券ならスマホで簡単に始められます。
- 月々5,000円からでもいい。インデックス投資の積立設定をする:まずは「S&P500」か「全世界株式」のどちらか1本で十分です。
- 金利のニュースで株価が下がったら、心の中でガッツポーズする:安く買えるチャンスが来たと考える。決して焦って売らない。
- 余裕資金ができたら、「債券ファンド」も少しだけ買ってみる:自分の資産がどう動くか、少額で試してみるのがおすすめです。
金利は、あなたを振り回す怖い怪物ではありません。その正体と付き合い方を知れば、これほど頼りになる道標はありません。ニュースの数字に一喜一憂するのではなく、その裏側にある経済の大きな流れを読み解き、自分の資産形成という長い旅の羅針盤として、賢く活用していきましょう。
-
前の記事

「ESG投資は儲からない」は本当か?懐疑派の意見を検証し、それでもSDGs投資が円安・インフレ時代の最適解である理由とは。 2025.10.06
-
次の記事

【もうお金で揉めない!】夫婦のための「最強の家計管理術」決定版|新NISA・iDeCo活用法からお小遣いルールまで徹底解説 2025.10.06