初心者必見!NISAとiDeCoの違いと選び方をわかりやすく解説
- 2025.10.08
- うさぎで学ぶシリーズ お金の基礎知識 投資戦略・テクニック
- iDeCo, NISA, 投資初心者, 節税, 資産形成

プロローグ
ここは、宇宙のどこかに浮かぶ「ふわふわ星」。なにもかもがフワフワしているこの星を、聡明でフワフワな王様、「てち王」が治めていました。今日も今日とて、ニンジン片手にご機嫌な王様のもとへ、元気いっぱいの妹姫の「ちろ姫」が駆け込んできたようです。
ちろ姫: 「にいさまーっ! 大変、大変! あたち、もっとたくさんリンゴが食べたいのー!」
てち王: 「おぉ、ちろ姫か。今日も元気いっぱいじゃのう。そんなに慌ててどうしたのじゃ? リンゴなら厨房にたくさんあるぞ?」
ちろ姫: 「ううん! そうじゃなくて! あたちのおこづかいを、もっといーっぱい増やしたいの! ぴょんぴょん増やして、自分専用のリンゴ畑を作るのが夢なの!」
てち王: 「ほっほっほ。自分専用のリンゴ畑か。それは壮大な夢じゃな。よし、面白いことを教えてやろう。朕が治める民、つまり地球の人間たちが使っておる、お金を増やすための『魔法の箱』の話じゃ」
ちろ姫: 「まほうのハコ!?」
てち王: 「うむ。その名も『NISA(ニーサ)』と『iDeCo(イデコ)』。この二つの箱は、おぬしのおこづかいを育てる手助けをしてくれるかもしれんぞ」
ふたつの魔法の箱「NISA」と「iDeCo」

ちろ姫: 「にーさ? いでこ? なんだかおいしくなさそうな名前ね…。どんな魔法なの?」
てち王: 「まぁ、焦るでない。まず『NISA』じゃが、これは『いつでもおやつを取り出せる、自由なガラスのおやつ箱』と考えると良い」
ちろ姫: 「ガラスのおやつ箱?」
てち王: 「そうじゃ。この箱におやつ(お金)を入れておくと、新しいおやつ(利益)が生まれることがある。そして、普通なら生まれたおやつのうち、いくつかを税金として国に納めねばならんのじゃが…このNISAの箱の中で生まれたおやつは、一つも納めなくてよいのじゃ! まるまる、自分のものになる」
ちろ姫: 「ぜーんぶ!? それはすごーい! あたちのリンゴも、誰にも取られずに済むのね!」
てち王: 「その通りじゃ。そして、中のリンゴが食べたくなったら、いつでも好きな時に取り出して食べられる。これがNISAの最大の特徴、『流動性が高い』ということじゃな」
ちろ姫: 「じゃあ、もう一つの『いでこ』っていうのは?」
てち王: 「うむ。『iDeCo』はな、『60歳になるまで絶対に開かない、頑丈な未来のおやつ箱』じゃ」
ちろ姫: 「えーっ! 60歳まで開かないの!? あたち、そんなに待てないわ!」
てち王: 「まぁ聞け。この箱は確かにすぐには開けられん。じゃが、その代わりにもっと強力な魔法がかかっておる。なんと、『箱におやつを入れた』というだけで、おぬしが国に納める税金が少しだけ安くなるのじゃ」
ちろ姫: 「え、入れるだけで? なんでなんで?」
てち王: 「それは国が『未来のためにしっかり準備する者は応援するぞ』と考えているからじゃな。これを『所得控除』と言う。さらに、NISAと同じで箱の中で増えたおやつにも税金はかからんし、60歳になって箱を開ける時も、税金がとても優遇される。まさに、未来の自分のための最強の箱じゃ」
どっちの箱がいいの? 仕組みを比べてみよう
ちろ姫: 「ふむふむ…。『いつでも自由なNISA』と、『未来のためのiDeCo』ね。でも、どっちの箱がいいのか、あたち迷っちゃうわ」
てち王: 「良い質問じゃな、ちろ姫。どちらが良いかは、人による。それぞれの箱の決まりを見ていこうかの。まず、箱を使える者じゃが、NISAは日本の18歳以上の者なら誰でも使える。iDeCoは基本的に20歳から65歳未満の、公的年金を納めている者が使えるぞ」
ちろ姫: 「箱に入れられるおやつの量は決まってるの?」
てち王: 「もちろんじゃ。NISAは年間に最大で360万円まで。iDeCoは、その者が会社員か、自営業か、それともおぬしのようなお姫様(専業主婦など)かによって、入れられる上限額が変わってくる。iDeCoの方が少し複雑じゃな」
ちろ姫: 「そっかぁ。じゃあ、箱の中には何を入れるの? ニンジン? 干草?」
てち王: 「ほっほっ。中に入れるのはお金じゃが、そのお金で『投資信託』などの金融商品を買うのじゃ。リンゴの苗木を買って、畑で育てるようなものじゃな。NISAとiDeCoで選べる苗木の種類も少し違うが、今は『どちらも色々な種類の苗木が選べる』と覚えておけばよかろう」
ちろ姫: 「わかったわ! でも、やっぱり一番の違いは、いつでも取り出せるかどうかなのね!」
てち王: 「その通り! よくわかってきたではないか、ちろ姫。それが最重要ポイントじゃ」
箱の注意書きと、うさぎさん別のおすすめ

てち王: 「ただし、ちろ姫よ。どちらの魔法の箱にも、小さな文字で書かれた『注意書き』があることを忘れてはならん」
ちろ姫: 「ちゅういがき?」
てち王: 「うむ。まずNISAじゃが、この箱の中で育てたリンゴの木が、天候不順で枯れてしまったとする(損失が出た)。残念ながら、その失敗を、隣のニンジン畑が大豊作だった(他の投資で利益が出た)からといって、無かったことにはできんのじゃ。これを『損益通算ができない』と言う」
ちろ姫: 「失敗は失敗として、自分で受け止めなきゃいけないのね…」
てち王: 「そういうことじゃ。一方、iDeCoの注意書きはもっとシンプルじゃ。さっきも言ったが、一度入れたら60歳まで絶対に引き出せん! よほどの緊急事態でも、この箱の鍵は開かんのじゃ。そして、箱を持っているだけで、ほんの少しだけ管理料(口座管理手数料)がかかることも覚えておかねばな」
ちろ姫: 「うーん、どっちも一長一短ね…。ねぇ、にいさま。ふわふわ星の、いろんなうさぎさんには、どっちがおすすめなの?」
てち王: 「良い視点じゃな。例えば、学校を卒業したばかりの若い世代なら、まずはいつでも引き出せる『NISA』から始めて、投資に慣れるのが良いかもしれん。結婚や引っ越しなど、急にお金が必要になることもあるからのう」
ちろ姫: 「なるほどー!」
てち王: 「子供を育てている世代なら、子供の将来の学費のためにNISAを使い、自分たちの揺るぎない老後のためにはiDeCoを使う、という合わせ技も強力じゃ。朕はこれを『二刀流』と呼んでおる」
ちろ姫: 「にとうりゅう! かっこいい!」
てち王: 「お仕事をしておらず、税金を納めていない主婦のうさぎさんでも、iDeCoの『運用益が非課税』というメリットは受けられる。じゃが、やはり所得控除の恩恵が大きい会社員や自営業の者の方が、iDeCoの魔法を最大限に活かせると言えるじゃろうな。ちなみに、iDeCoの箱は、転職して職場が変わっても、ちゃんと次の職場に持っていける(ポータビリティ)から安心するのじゃぞ」
大事なのは「自分のための箱」を選ぶこと
ちろ姫: 「そっかぁ…。リンゴ畑を作る!っていう夢のためなら、いつでも取り出せるNISAの方がいいのかも。でも、ずーっと先の、おばあちゃんになったあたちのための箱も、あったら安心ね…」
てち王: 「うむ。その通りじゃ、ちろ姫。NISAとiDeCo、どちらが優れている、という話ではない。おぬしが『いつ』『なんのために』お金を育てたいのか。その目的によって、選ぶべき箱は変わってくるのじゃ」
ちろ姫: 「あたちの目的…」
てち王: 「そうじゃ。すぐにリンゴ畑を作りたいのか、それとも王女として立派に暮らす未来の自分のためか。まずはそれを考えることが、資産形成の第一歩じゃ。この記事を読んでくれている人間たちも同じじゃぞ。二つの箱の違いがスッキリと理解できれば、今日はそれで大成功。焦らず、自分の人生という物語に、どちらの箱が必要か、ゆっくり考えてみてほしい」
ちろ姫: 「わかったわ、にいさま! あたち、自分の目的、よーく考えてみる! そして、いつか絶対、自分だけのリンゴ畑を作ってみせるわ!」
こうして、ちろ姫の新たな挑戦が始まりました。NISAとiDeCo、二つの魔法の箱の特性を理解したあなたは、どんな未来を描きますか? まずは自分のライフプランを考えるところから、始めてみてはいかがでしょうか。
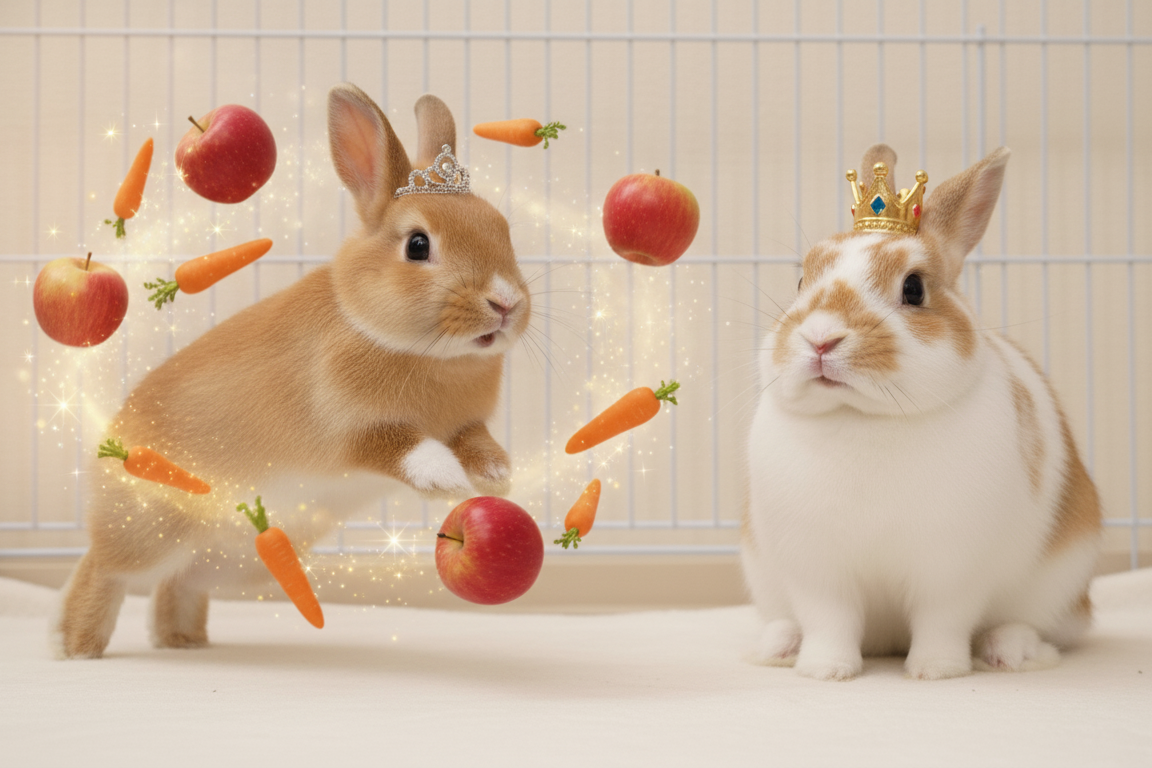
補足解説コーナー
- iDeCoの3つの税金メリット
- 掛金が全額所得控除:iDeCoに入金したお金は、その年の所得から全額差し引くことができます。これにより、所得税や住民税が安くなります。会社員や自営業の方には非常に大きなメリットです。
- 運用益が非課税:通常、投資で得た利益には約20%の税金がかかりますが、iDeCoの口座内ではこれが一切かかりません。NISAと同じ強力なメリットです。
- 受け取る時も控除がある:60歳以降に一時金として受け取る場合は「退職所得控除」、年金として分割で受け取る場合は「公的年金等控除」という税金の優遇措置が適用されます。
- 損益通算(そんえきつうさん) 複数の投資を行っている場合に、一方の利益と、もう一方の損失を合算することです。例えば、A株で10万円の利益、B株で5万円の損失が出た場合、損益通算すれば利益は5万円と見なされ、税金の負担が軽くなります。NISA口座での損失は、この損益通算の対象にできません。
- ポータビリティ 「持ち運び可能」という意味です。iDeCoは、加入者が転職・退職しても、それまで積み立てた資産を次の加入資格(企業の年金制度や個人型など)に引き継ぐことができる制度です。
- 口座管理手数料 iDeCoの口座を維持・管理するために、毎月かかる費用のことです。金融機関によって金額が異なりますが、加入時には必ず確認しておきたいポイントです。
-
前の記事

日銀の『イールドカーブ・コントロール』って何?経済の仕組み 2025.10.08
-
次の記事

日銀のインフレ目標とは?物価上昇と生活への影響をわかりやすく解説 2025.10.08